当サイトでは漁村の活性化に向けた取り組み事例を紹介するとともに、平成20年度に行われた地域リーダー育成研修会やシンポジウムの内容、地域と連携した活動を行っている大学や企業などを紹介しています。
活力ある漁村づくり研修会・シンポジウム
過去の研修会・シンポジウム
都市漁村交流の普及啓発
1)開催趣旨
活力ある漁村づくりモデル育成事業では、多様な地域性や取組の体制の中で、地域それぞれが漁村地域の活性化を目指した取組を進めている。これら各地での漁村地域の活性化についての取組から、地域の個性にあわせた漁村の活性化のあり方、その方法について考える場として、シンポジウムを開催した。
【プログラムの構成】
●基調講演
【プログラムの構成】
●基調講演
- 漁村の活力づくりについて、その手法を全国の事例や政策、社会動向を紹介する
- 漁村地域での実践者などの参加者から関心の高い水産物のブランド化や流通、都市漁村交流について、実施のポイント、効果や課題などをお話いただく。
- 後段の事例紹介のイントロダクションとして、活性化手法とその全国的な状況を概況いただく。
- 活力ある漁村づくりモデル育成事業での取り組み事例として、北海道厚岸地域(主にブランド水産物づくり、流通改良の事例)、北海道根室市落石地域(主に地域の景観資源や海鳥を活かし漁業を基軸とした観光事業の事例)、沖縄県竹富町小浜島細崎地域(小規模離島でのブルーツーリズム)での取組を紹介いただく。
- 本事業での検討を進める漁業の多角化に関する事例として、長崎県上対馬地域での取組(漁具漁法の導入による漁業の振興)を紹介いただく。
- 地域それぞれの取組内容と手法について、参加者に知ってもらう。
- 取組の成功とは何か、地域の活性化とはどのような状態で、地域の取組は何を目指すのか、漁村の活性化について、地域それぞれの目標設定や具体的な進め方、一方での漁村地域で共通するポイントなどを議論する。
2)実施概要
| 日時: | 平成23年3月9日(水曜日)14時〜18時(開場13時半) |
|---|---|
| 場所: | 東京コンベンションホールAP浜松町 会議室F (東京都港区芝公園2-4-1ダヴィンチ芝パークB館地下1階) |
| 参加者数: | 84名、全国の漁村活性化の関係者(漁業者、漁協、行政、研究者、企業、学生他) |
3)実施結果
| 漁村の活性化とは何か 〜漁村地域での活力づくり実践例から考える |
|
| 主催者挨拶 | 水産庁漁港漁場整備部長 |
| 第一部 基調講演 |
講演Ⅰ 水産物のブランド化、新たな流通による漁村活性化 はこだて未来大学 長野教授  講演Ⅱ 都市漁村交流による漁村活性化 近畿大学 日高准教授  |
| 第一部 事例紹介 |
【事例Ⅰ 北海道厚岸地域】 新たな流通の仕組みづくりによる水産物の高付加価値化 二次元バーコードを使った生産履歴情報発信の仕組みづくり  【事例Ⅱ 長崎県上対馬地域】 新漁法の導入による地域の漁業振興と漁村活性化 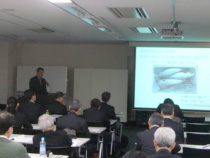 【事例Ⅲ 北海道根室市落石地域】 地域の野鳥に注目したネイチャークルーズの実施と漁村活性化  【事例Ⅳ 沖縄県竹富町小浜島】 小規模離島での漁業・水産物を活用したブルーツーリズムの推進  |
| 第二部 パネルディスカッション |
【パネリスト】 はこだて未来大学 長野教授 , 近畿大学 日高准教授 , 厚岸漁協市場部川尻部長 , 長崎県上対馬漁協漁業士 , 落石漁協専務理事 , 小浜島 まーる新鮮隊 【コーディネータ】 高知大学受田教授 【テーマ】 漁村の活性化とは何か  目指すべきところは水産物の価格向上、漁家個人の収入アップといった共通のところから、漁業後継者が帰ってこられる地域をつくること、そのための確かな産業をつくることを目標に取組を進める地域の意見もあった。様々な将来像を持つ一方、地域での課題としてはやはり事業の担い手をいかに確保し、地域一体での取りくみを進めるかという部分であることが話し合われた。人材の確保育成にくわえて、市場施設の更新、ITをうまく使って情報発信と消費者の情報を収集することの必要、市場からの情報をいかに生産地にフィードバックさせるか、特に交流事業ではプログラムを更新し続けることの必要を有識者の先生方からも意見いただいた。 最後に漁村地域間のつながりにより、全国的な運動として漁村の活力づくりをすすめることについての意気込みを登壇者一同で示していただき閉会となった。  |
お問い合わせ
ランドブレイン株式会社
TEL:03-3263-3811
email:gyoson@landbrains.co.jp
Copyright (C) 2010 Landbrains CO.,LTD. All Rights Reserved.
本サイトは、水産庁委託事業(活力ある漁村づくり促進委託事業)によりランドブレイン株式会社が運営するものです。
本サイトは、水産庁委託事業(活力ある漁村づくり促進委託事業)によりランドブレイン株式会社が運営するものです。